授業ネタの動画投稿のお知らせ:「ヨーロッパ」
sogeoです。授業で話すと興味を引ける小話の動画を「地理の総合力 動画館」にアップロードしました。こちらから動画販売ページに移動することができます。地理を担当することになる教員の方に、うまく活用していただければと思います。
今回は、「気候」あるいは「地図(球体としての地球)」で扱うと効果的な小話です。中学社会でも「世界の気候」などで使えます。地理総合における大項目A(1)「地図や地理情報システムと現代世界」や、地理探究における大項目A(1)「自然環境」でも活用できそうです。
実践の概説
太陽光線が分散せずに届く赤道付近は、気温も高く、水蒸気も発生しやすいため、雨の降りやすい赤道低圧帯が形成されます。そして、地軸が傾いている状態で地球の周りを公転していることによって、気圧帯の移動が生じ、時期によって乾燥したりする地域が出てくるなど、気候の年変化が起こります。
ところで、気候の英単語「climate」の由来は……? 英語には、ノルマン・コンクェストのころにはフランス語、そしてルネサンス期にはギリシャ語やラテン語などの語彙が入ってきますが、由来を辿ってみると、面白い繋がりが感じられます。ドイツ語の「Klima」など、ヨーロッパ全土で似た言葉で表される「気候」ですが、すべての元はやはりアレから来ているのですね。
用語が出てきたときは、一緒に英単語も併記しておくことで、単純に英語学習にもなるほか、いろいろな繋がりが生じて「ハッ」とする機会を増やすことができます。授業中の話の流れが分かる動画を公開しておりますので、こちらからぜひご覧ください。
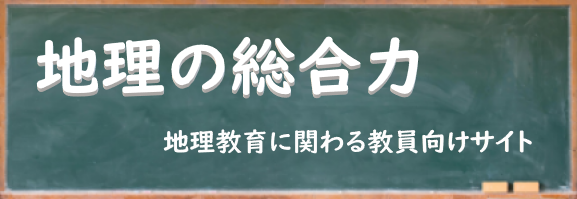

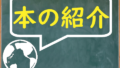
コメント