授業ネタの動画投稿のお知らせ:地図
sogeoです。授業で話すと興味を引ける小話の動画を「地理の総合力 動画館」にアップロードしました。こちらから動画販売ページに移動することができます。地理を担当することになる教員の方に、うまく活用していただければと思います。
今回は、高校地理・中学地理の「地図(図法)」で扱うと効果的な小話です。地理総合の大項目A「地図や地理情報システムで捉える現代世界」のテーマなどでも活用できます。
実践の概説
一般的な世界地図は、角度が正確になるように作られたメルカトル図法、あるいはそれに準ずるものが採用されています(地図帳の1ページ目にあるものはミラー図法)。多くの人が慣れ親しんでいる図法ですが、これは高緯度ほど面積が大きく引き伸ばされているため、ヨーロッパやアメリカなどが必要以上に大きく見えてしまい、誤った地理・歴史観を与えてしまうのではないかという意見もあります。
そこで、面積の拡大比率を調整(高緯度は横方向への引き伸ばしがある分、低緯度地域は縦方向に引き伸ばすことで帳尻を合わせる)することで面積比を保った図法があることを紹介します。時間軸は違えど考案に携わった2人の人物、アルノー・ピーターズとジェームス・ガルの名前がつけられた、「ガル・ピータース図法(ゴール・ペータース図法)」です。
教材提案だけでなく、授業中における話し方も感じていただける動画をアップロードしておりますので、こちらからぜひご覧ください。
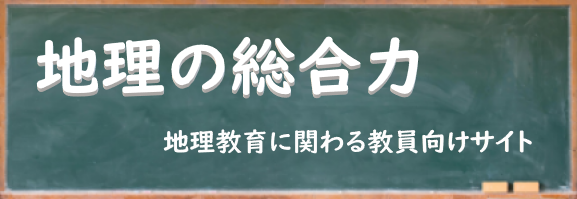


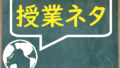

コメント