授業ネタの動画投稿のお知らせ:「鉱工業」
sogeoです。授業で話すと興味を引ける小話の動画を「地理の総合力 動画館」にアップロードしました。こちらから動画販売ページに移動することができます。地理を担当することになる教員の方に、うまく活用していただければと思います。
今回は、高校地理の「鉱工業」などで扱うと効果的な小話です。中学社会でも「日本の産業」を学ぶときに使えそうです。地理探究における大項目A(2)「資源、産業」などでも活用できそうです。
実践の概説
高度経済成長期に大きく力をつけた日本ですが、その後の石油危機や円高を背景に、輸出不振に陥って大ダメージを受けてしまいます。貿易摩擦などの問題もあり、これまでの加工貿易主体の経済を変えていく必要性から、日本は工場を海外に移し、現地生産を行うという手段を取ることが増えていきました。それが、国内に技術が蓄積しない「産業の空洞化」として問題視されます。
ただ、これは本当に悪いことなのでしょうか? 資本主義的な商売の観点から考えれば、「問題となる点を回避し、コストを下げ、良い製品を届けるために工夫する」という行動自体は何ら悪いことではなく、むしろより多くの人に便利なものを届けることによって世界全体が得をしそうです。安価な労働力を抱える東南アジアなどに工場が進出するのも、(経済格差的な視点の問題は別にありますが)新たな雇用を生み、国際的な発展に繋がりそうです。「日本国内に技術が残らない」というのも、ボーダーレス化が進んでいる国際社会では、些末なことになっていくかもしれません。
安価な労働力を利用することがすぐに「搾取」に繋がるのではなく、より多くの人が得をする行動となる。そういった考えた方もありうるでしょう。そのことを、生徒も親しんでいそうなYouTuberという仕事を題材に投げかけています。本当に「その人だけが持つ価値を活かす」ために、どのような在り方が増えているか? 題材の提案だけでなく、授業中の話し方も感じていただける動画をアップロードしていますので、こちらからぜひご覧ください。
多少、明確な根拠を用いて話しているというよりは個人の感想としての側面も強い内容ですので、利用の際は各人で検討したうえで利用可否を判断し、自分の言葉でアレンジしていただければと思います。
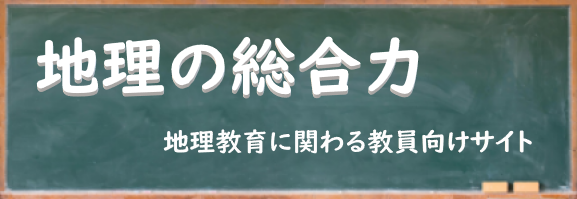


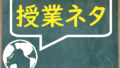
コメント