動画投稿のお知らせ:地理総合の授業づくり
sogeoです。2022年度から始まる地理総合の授業を担当する教員向けに、地理総合の各授業で話すと効果的な内容について、授業時のコツなどを紹介する動画シリーズを投稿しています。
今回は第2回。地理総合の柱A「地図や地理情報システムで捉える現代世界」の内容の2回目です。こちらから動画販売ページに移動することができます。前編と後編に分かれています。地理を教え慣れている教員の方も、初めて地理を担当する教員の方にも、うまく活用していただければと思います。
実践の概説
第2回では、第1回で扱った緯度経度などの「地球の姿」を踏まえて、それを地図に落とし込むところについてです。世界地図はいろいろな図法が用いられますが、球体を平面にするには限界があり、角度や面積などいくつかの要素が犠牲になります。用途に応じて使い分けることで対応しています。
また、国内の観光地に出かける際に世界地図を持って出かける人はいないわけで、より狭い範囲を映した地図の方が日常ではよく使われます。そこでも、「ここが果樹園、ここが田んぼ……」などの情報は不要だったりするので、必要な地理情報のみを中心的に取り上げた主題図というものが多く出てきます。
取り上げている内容としては、以下のようなものがあります。
- 地理Bから削減:光源の位置(心射、平射etc)、書き写し方(円筒、円錐etc)
- 「正しさ」だけが正義じゃない。何もかも正しくない地図も活用。
- メルカトル図法が生む「誤解」、国の大きさ
- 緯度60°地点は、2倍に拡大。cos60°が掛け算。
- 正距方位図法も、デジタルならいくらでも作れる
- 観光地マップに「ここに針葉樹があるのかぁ」は要らない
- いったい何までが地図?(間取り図? 映画館の座席図?)
こちらからぜひご覧ください。地理総合の授業づくりの一助となれれば幸いです。今後も活動を続けられるよう、何卒ご支援をよろしくお願いいたします。
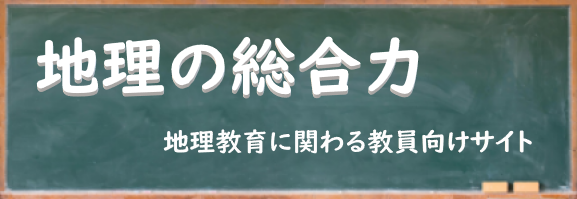
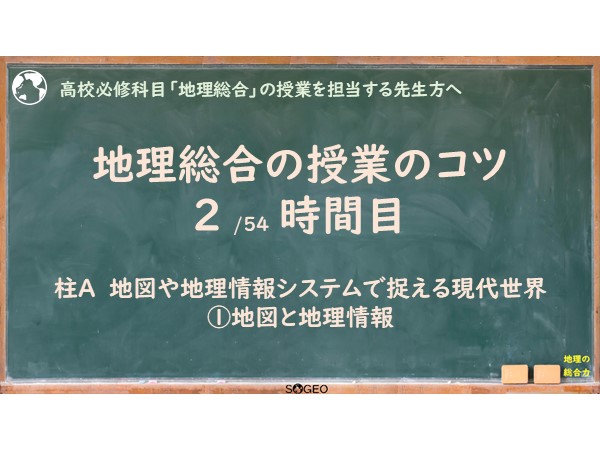


コメント