動画投稿のお知らせ:地図
sogeoです。授業で話すと興味を引ける小話と、授業中に提示すると効果的なサイトの紹介をしている動画を「地理の総合力 動画館」にアップロードしました。こちらから動画販売ページに移動することができます。地理を担当することになる教員の方に、うまく活用していただければと思います。
今回は、高校地理の「地図(図法)」などで扱うと効果的な小話です。中学社会でも、「世界の姿(世界地理の基礎、導入)」を学ぶときに使えそうです。地理総合における大項目A(1)「地図や地理情報システムと現代世界」などでも活用できそうです。
実践の概説
図法の学習をする際、主なものとして取り上げられるのは、角度の正しいメルカトル図法、面積の正しいモルワイデ図法、そして中心からの距離と方位が正しい正距方位図法の3つがはじめに挙がってくることでしょう。
世界全図として1枚で完結させられる前2つの図法に対して、正距方位図法は「中心から」の距離と方位しか正しくならないことは注意しなくてはなりません。つまり、中心をどこに設定するかによって、その枚数分の地図が必要になります。東京を中心とした正距方位図法、ロンドンを中心とした正距方位図法、ニューヨークを、シドニーを……。世界の各地点からの距離と方位を認識するためには、無限に地図が必要になります。
そこで、こちらの「どこでも方位図法」が役に立ちます。ドラッグすることで、任意の地点を中心に置いた正距方位図法を作成することができます。東京を中心にしたとき、図の円周部分で大きく引き伸ばされている場所が南米であることは、生徒はなかなか認識するのが難しいです(北米がある程度自然な形をしているので尚更)。しかし、ぐりぐりと中心を動かすことで、世界各地が形を変え、中心の裏側に位置する地域が引き伸ばされる様を実感することができます。
生徒1人1人がICT機器を扱える環境なら、実際に触らせれば効果的でしょう。各人、好きな場所を中心にさせ、そこから分かること(〇〇大陸がどの方位にある、距離はどのくらい……など)をまとめて提出・発表させる等を行えば、立派な探究活動になり、生徒が分担していろいろな正距方位図法を提示してお互いに学び合うことができます。
サイトの紹介を、画面キャプチャを用いながら解説しているとともに、授業中における扱い方も感じていただける動画をアップロードしていますので、こちらからぜひご覧ください。
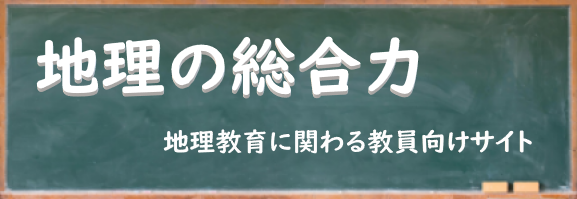
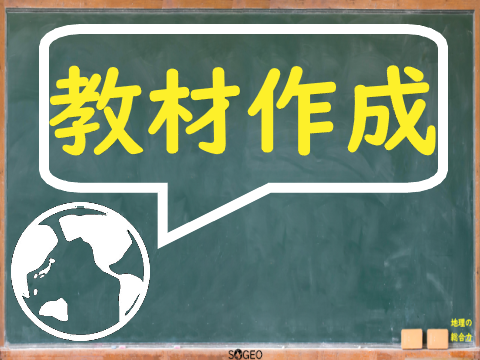

コメント