ラクして生きていきたいなら地理
sogeoです。「地理を何のために学ぶのか」「人口とか面積とか、ネットで調べたらすぐに出てくる話が多いのにやる意味が分からない」といった声は、よく聞かれます。
地理を学ぶことで得られるメリットは、「人生をラクに生きる方法が分かること」と説明することにしています。少し意外な返答らしく、大きく出たな、という気持ちが生じるため、生徒も食いついてきやすいと感じています。以下でもう少し掘り下げていきます。
地理は未来予測の科目
ラクに生きる、ということの1つには、将来などに不安や心配を抱えずに生きていく、ということが含まれているということができるでしょう。「恐怖は未知から生じる」ーー人間は誰しも、自分の将来が不安になるものです。変化の激しい時代、不安の種は尽きません。その状態から脱することを目指すには、「地理」の力が大いに役立ちます。
なぜなら、地理で学ぶ今の世の中の姿は、少し前の世代の人の、「こんな感じだったらラクに楽しく生きていけるのにな」という思いが結実して成立しているものだからです。スマホ、飛行機、電車、コンビニ弁当など身の回りのいろいろな物も、「こういうものがあったら便利だしラクだ」という思いで生まれています。また、広大な平野のある場所に大勢の人が集まった結果として首都圏が成立しているのも、「物を運ぶにも鉄道の線路を引くにも、平坦なところの方がラクだ」と考えて行動した結果でしょう。
例えば農業という営みが始まったのも、狩猟採集だと安定しませんから、「近くで安定して食べ物が採れないかな」と考えた人が始めたと推測できそうです。また、それが発展していくと、「この土壌の土地だとこっちの作物の方がよく育つな(生産性が高くてたくさん採れるので「ラク」)」「こんな肥料を使えばもっと採れてラクだな」「寒さに強い品種ができたらもっと採れてラクだな」……と、欲望の肥大化に伴って技術が発展していったといえます。
人間の「ラクして生きていきたい」という普遍の思いが社会を作っていくのだから、人々の「ラクして生きていきたい」気持ちによって作られてきた今の世の中を地理で紐解くことで、自分たちがこの先突き進んでいく未来を「ラクに生きていく」ヒントも発見できる。時代の変化は踏まえつつ、今の人々がどのような社会を「ラク」だと望んでいるのかを見つめるきっかけになり、そこから未来を予測、あるいは発明や行動によってその未来を自ら作り出すことができる。未来の展望が見えやすくなることで、未知を減らすことができます。
「ラクしたい」は何ら悪いことではない
同時に、「ラクして生きていきたい」という気持ちが、悪いものではないという安心感も抱けることになります。一生懸命頑張ることだけが美徳なのではなく、多くの人の「ラクしたい」という気持ちが世界を形作ってきたのです。だから自分も「ラクして生きたい」と考えて一向に構わない。むしろ、そういった考え方を持っている人の方が、地理を活用して未来を良くしていくことができるかもしれません。
自分が「こうなるとラクだ」と思っているのだから、きっと他の人間も同じように思っているはず、つまりそこに需要があるからこんな商品・サービスを作って世の中に出そう! ……という行動ができる人、すなわち起業家が増えれば、世の中はどんどん便利になっていきそうです。もちろん、行動を起こした人はお金も儲けられる可能性が高い。地理を学ぶ人が増えれば、GDPやGNIの向上も期待できそうです。
そんな思いで地理教育に携わっています。今後もいろいろな観点から地理について考えを垂れ流したいと考えています。
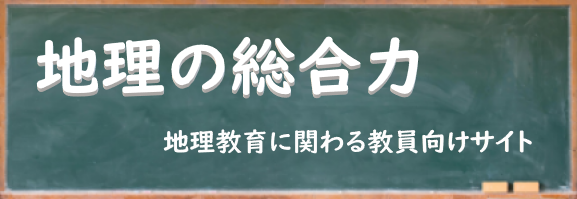

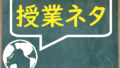

コメント